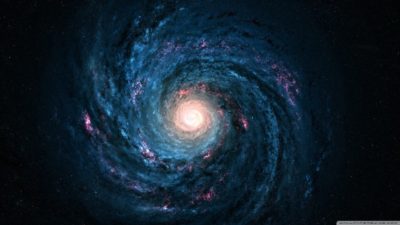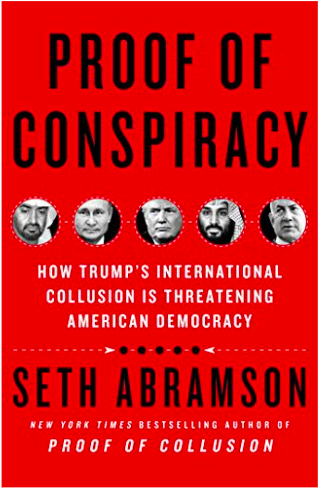藤田省三という思想家がいます。
古い人ですが、丸山真男の弟子で、現代の社会状況を、言い当てています。
以下は藤田省三の著書からの引用です。少々長いですが、引用しますね。
『抑制のかけらも無い現在の「高度技術社会」を支えている精神的基礎は何であろうか。言い換えれば、停どまる所を知らないままに、ますます「高度化」する技術の開発を更に促し、そこから産まれる広大な設備体系や完結的装置や最新製品を、その底に隠されている被害を顧みることもなく、進んで受け容れていく生活態度は、一体どのような心の動きから発しているのであろうか。「追いつき追い越せ」から「ますます追い越せ」へと続いて来ている国際競争心等々の他に、少なくとも見落としてはならない一つの共通動機がそれらの態度の基底に在って働き続けている。
それは、私たちに少しでも不愉快な感情を起こさせたり苦痛の感覚を与えたりするものは全て一掃して了いたいとする絶えざる心の動きである。苦痛を避けて不愉快を回避しようとする自然な態度の事を指して言っているのではない。むしろ逆に、不快を避ける行動を必要としないで済むように、反応としての不快を呼び起こす元の物(刺激)そのものを除去して了いたいという動機のことを言っているのである。苦痛や不愉快を避ける自然な態度は、その場合その場合の具体的な不快に対応した一人一人の判断と工夫と動作を引き起こす。
通常の意味での回避を拒否して我慢を通すことさえもまた不快感を避ける一つの方法である。そうして、どういう避け方が当面の苦痛や不愉快に対して最も望ましいかは、当面の不快がどういう性質のものであるかについての、その人その人の判断と、その人自身が自分の望ましい生き方について抱いている期待と、その上に立った工夫(作戦)の力と行動の能力によって始めて決まって来るものである。そこには、個別的具体的な状況における個別具体的な生き物の識別力たる生活原則と智慧と行動とが具体的な個別性をもって寄り集まっている。すなわち其処には、事態との相互的交渉を意味する経験が存在する。
それに対して、不快の源そのものの一斉全面除去(根こぎ)を願う心の助きは、一つ一つ相貌と程度を異にする個別的な苦痛や不愉快に対してその場合その場合に応じてしっかりと対決しようとするのではなくて、逆にその対面の機会そのものを無くして了おうとするものである。そのためにこそ、不快という生物的反応を喚ぴ起こす元の物そのものを全て一掃しようとする。そこには、不愉快な事態との相亙交渉が無いばかりか、そういう事態と関係のある物や自然現象を根こそぎ消滅させたいという欲求がある。恐るぺき身勝手な野蛮と言わねばならないであろう。
かつての軍国主義は異なった文化社会の人々を一掃殲滅することに何の躊躇も示さなかった。そして高度成長を遂げ終えた今日の私的「安楽」主義は不快をもたらす物全てに対して無差別な一掃殲滅の行なわれることを期待して止まない。その両者に共通して流れているものは、恐らく、不愉快な社会や事柄と対面することを怖れ、それと相亙的交渉を行なうことを恐れ、その恐れを自ら認めることを忌避して、高慢な風貌の奥へ恐怖を隠し込もうとする心性である。
今日の社会は、不快の源そのものを追放しようとする結果、不快のない状態としての「安楽」すなわちどこまでも括弧つきの唯々一面的な「安楽」を優先的価値として追求することとなった。それは、不快の対極として生体内で不快と共存している快楽や安らぎとは全く異なった不快の欠如態なのである。そして、人生の中にある色々な価値が、そういう欠如態としての「安楽」に対してどれだけ貢献できる ものであるかということだけで取捨選択されることになった。「安楽」が第一義的な追求目標となったということはそういうことであり、「安楽へ隷属状態」が現れて来たというのも又そのことを指している。休息すなわち一と時の解放と結びつくのであって、楽しみや安らぎなら隷属状態とは結びつかない。
むろん安楽であること自体は悪いことではない。それが何らかの忍耐を内に秘めた安らぎである場合のひとには、それは最も望ましい生活態度の一つでさえある。価値としての自由の持つ第一特性である。他人を自由にし他人に自発性の発現を容易にするからである。しかし、或る自然な反応の欠如態としての「安楽」が他の全ての価値を支配する唯一の中心価値となって来ると事情は一変する。それが日常生活の中で四六時中忘れることの出来ない目漂となって来ると、心の自足的安らぎは消滅して「安楽」への狂おしい追求と「安楽」喪失への焦立った不安が却って心中を満たすこととなる。
こうして能動的な「安楽への隷属」は「焦立つ不安」を分かち難く内に含み持って、今日の特徴的な精神状態を形づくることとなった。「安らぎを失った安楽」という前古未曾有の逆説が此処に出現する。』(藤田省三:「全体主義の時代経験」)
引用ここまで。
藤田省三が言わんとするところは、現代社会に生きる我々のこの「安楽への隷属」の病理が抜きがたく進行しているということ、これがある社会現象を必然的に引き起こすということです。
「安楽への隷属」は、苦痛を生じさせる場合を限りなく少なくする方向に働きます。現代人が対峙しうる苦痛の経験を限りなく小さくします。経験とは、つまり、単なる過去の事実ではなくて、具体的状況における判断や思索のことです。そして、その経験そのものが苦痛を伴わないようにアレンジされていますので、経験からさまざまな物事を学び取ることが出来にくくなっています。
また、社会が高度に専門技術的に細分化されてその範囲内(ごく限られています)でしか、人間は考え行動することができません。社会的に尊敬されるべき人々も、経験が限られているから、全人的に成熟することができないのです。概してそういう人は、恐ろしく幼稚です。しかも、それを他人に気取られまいと常に不安でいっぱいです。かつてならば、生活のなかで当然に身につくはずだった人間としての全体性や完全性がどの人にも存在しません。みんなどこかいびつで不均衡発達をしています。おまけに、共感することが出来ません。人の感情を思いやることができないのです。
心の平安とは、悩み抜いてたどり着くはずの境地なのに、希薄な経験から希薄な悩み、その悩み自体も放棄して、ある意味偽りの平安に逃げ込みます。しかし、いつこの偽の平安が破られるかも知れず、心は不安でいっぱいです。そして、この均衡が少しでも破られるとすぐに不機嫌になるのです。
加えて、経験から不快な苦痛の生ずる機会を極力なくす社会の下では、人間に試行錯誤して発達することを許しません。最初から完璧を期待され、最初からいかに完璧に出来るかで序列化されます。人間性が精神的に非常に窮屈で貧しいものになってしまっています。
全てにおいて最初から完璧で決して失敗せず、不快な状況を作らないような人が求められます。そんな人はいません。こういうないものねだりをしたあげく、勝手に失望してしまうのです。
こういう状況では、主体性を個人に期待しても、ものすごく難しい。
個人は、自分のことで精一杯です。自分のこの偽りの平安を乱されたくないのです。例えば、アホな上司が気まぐれで、その気まぐれに怒鳴られるのが嫌だから、アホな上司に迎合して、偽りの平安を求める、みたいなことです。一流企業では、最近はパワハラなんていう便利な言葉がありますから、そんなことしなくても済んでいるかも知れませんが、中小企業、フリーランスはまだまだ、そういうことが日常茶飯事なのですよ。
そして、余裕がありませんから、人々は、他人には恐ろしく「無関心」で、自分さえよければ他人はどうでもいい、という「利己心」で凝り固まっています。自分の心の平安を求めるため、公共心を失っていくのです。
そうすると、この先どうなるか。社会のために自分で主体的な選択をすることを避け、社会全体が、ひとつの方向性、つまり、みんながみんなに迎合して、みんながする選択をみんなでする、という方向に向かうのです。
摩擦や軋轢を意図的に生じさせて権力の乱用を防ぐのが、民主主義的制度なのに、肝心の摩擦や軋轢が最初から排除されてしまうので、権力の乱用に対する歯止めが効きません。政治は結局数の論理となり、「国民のため」とか、「日本に危機感を持って立ち上がる」とか、耳当りのよい中身のない美辞麗句を挙げ独善的な政策をかかげて、絶対多数をとることを目指して、ナルシズムを気取る茶番になってしまう。そして、そんな政権でも、選挙で絶対多数が取れてしまう。
こうなると民主主義は、ものすごく効率の悪い制度に見えてきてしまう。
しかし、かつてのドイツのカールシュミットとケルゼンの論争におけるように、論説さわやかに明快な理論をかっこよく打ち上げ、いわば大衆受けする方が勝利して、巧妙に民主主義を否定するような方向にすすんだことをよく思い出さねばなりません。ただ、一方、今の日本が民主主義の危機なのは、違う理由によります。おそらく、現政権が無知であることは、この政権がやりたい放題やっていることと関係しています。現政権は、批判してもちっともこたえません。どうして批判なのか、無知で、わかっていないからです。自由や民主主義、立憲主義と言った、過去何百年の血の池を通ってようやく実現した価値観を意に介していないからです。そうでなければ、例えば、古くは集団的自衛権の行使について、閣議決定で可能になど出来ないでしょう。立憲主義を知っている宰相なら、歴代、怖くて出来なかったでしょう。それを、しれっと、やってのける。
野党は、そういう観念的な人権観、憲法観に立って批判していて、それは、西欧立憲主義からすると伝統的な批判ななのですが、現政権、とりわけ、現宰相は、勉強していないので、全くわかっていないのです。だから、批判が彼にはちっともこたえません。自分を恥ずかしいと思っていない、それどころか、自分は正しいことをやっていると本気で思っているでしょう。
そして、立憲主義的観点からは、自分のやっていることが、とんでもなく危険なこと、という認識がないのです。自分のやっていることが、いわば、立憲主義を無視した、「柔らかい独裁主義」であることをわかっていないのです。そして、この「柔らかい独裁主義」を支える風土が日本社会にはそもそも昔からあるのだと言えます。
昔、「日本は天皇制がある限り独裁者は出ない」なんて言ってた人がいましたが、そうじゃないと思います。戦前の軍部の独裁は、独裁者がいたわけではないのです。恐ろしく国民に無関心で、自己の利益のみを図ろうとする軍部機構を含む官僚機構全体とそれに結託した産業界、マスコミが全部一つになって、つまり庶民に対して権力を持っていた存在自体が一体となって、そして、当の庶民もそれに加担して成立した不思議な体制だったわけです。いわば独裁者なき独裁体制だったのです。産業界もマスコミも、国民もそれに加担して成立した独裁体制です。そして、その根底は、「忖度」なんです。権力者が、「忖度しろ」「自粛しろ」というと、波風立てたくないので、「自然とそうなる」のが日本社会なのです。しまいには、権力者が、「忖度しろ」と言わなくても、「忖度する」のが当たり前になるのです。そして、そこには、表面的には「憲法の人権に配慮した」「恐ろしく残酷な自己犠牲」を強いるとっても気持ち悪い構造があるのです。しかも、日本では、反乱も、暴動も起きない。この総国民的な自粛生活の中で、耐えられない人々が、静かに限界を迎え次々と死んでいくわけです。しかし、権力者は、自分の生活が脅かされるわけではないので、全く意に介しません。
もしかすると、状況はもっと酷くて、日本国民の6割は意に介さず、4割の人々にしか解らない脅威があるのかも知れない。現在の自粛生活で、生活の糧を失った人々は、死活問題であるのに、6割の人々はそれがあまりわかっていないのかも知れない。自宅で静かに死んでゆく人々が見えないですから。そうだとすると、欧米のような、国家の9割の富を1割の人々が独占している、という状況ではない、つまり、6割の人にとっては、現在の状況はまあ、なんとか生きていけるので、たいしたことではなく、4割の人々の死活問題は社会問題化しない。6割の人々の幸福や安全を4割の人々の犠牲によって実現していて、6割の人々はそれに気づかない。権力者は6割の人々の代表だから、生きるか死ぬかの問題に直面している4割の人たちのことは気にもかけない。日本の社会には、もしかすると、こういうことが起きているのかも知れない。そして、4割の人たちは、6割の人々が享受している幸せも享受できずに、静かに死んでゆくしかないのかも知れない。
そして、話を元に戻すと、いわば、この「6割の全体主義」ほど、タチの悪いものはないかも知れない。現代日本のこの「6割の全体主義」には、戦前のドイツや日本よりもはるかに巧妙で強力でさらに邪悪なものがうごめいているのを感じます。
そして、この「6割の全体主義」の火に油を注いでるのは、とりもなおさず、6割の人たちの、恐ろしく無能な権力者たちへのいわば「不安定な安楽」に支えられた、「安楽への隷属」であるところの「忖度」、「自粛」である、ということを忘れてはいけないと思います。
長々と書いてしまいました。また、考えをまとめて再びいつか、もっと簡潔に書いてみたいと思います。
最後まで読んで頂いてどうもありがとうございます。